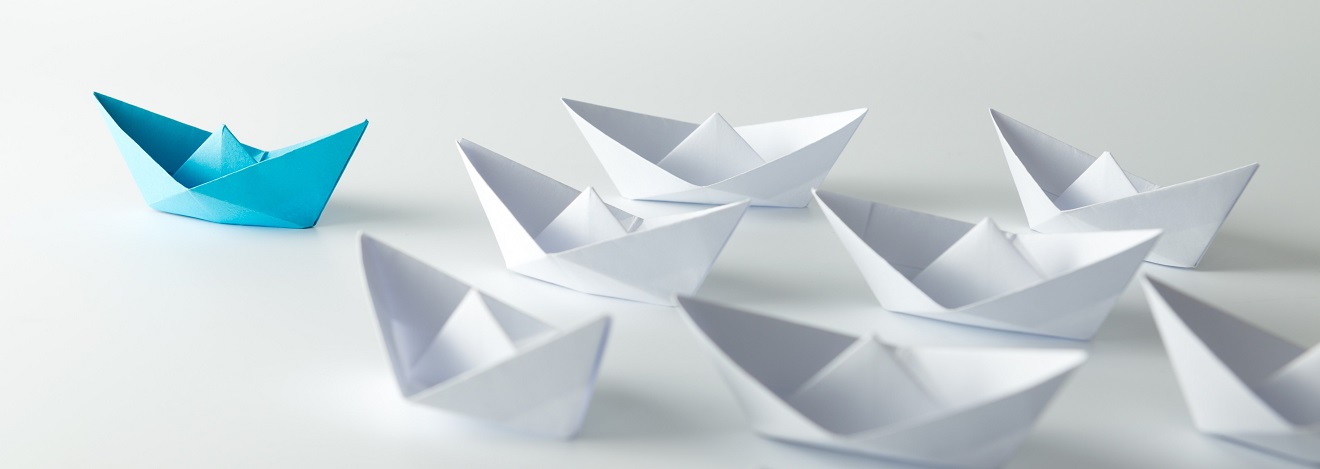企業が売上げ目標を達成するためには、適切な組織運営が不可欠です。組織はさまざまな人間の集合体と言えます。さまざまな人の考えや意見を取り入れて、一つの目標に合わせて組織を効率よくマネジメントしていくことが大切です。
とは言え、上手く運営しなければ、メンバーそれぞれが自由な行動を行ってしまい目標の方向に向かわなくなってしまったり、社内コミュニケーションが円滑にとられなくなったりと、組織の良さが生かされなくなってしまうこともあります。
本記事では、組織運営の概要や組織運営を行う上で必要な7つのS、管理者に求められる能力についてご紹介します。

組織運営とは
組織運営とは、目標達成に向けて組織の活動を円滑に行えるように、会社の経営資源を管理者がマネジメントすることです。ここでの主な経営資源は「ヒト(社員)」「モノ(商品や設備)」「カネ(資金)」「情報」を表しますが、中でも「ヒト」は特に重要になります。
組織は同じ目的や目標に向かう「ヒト」の集合体であり、営業活動のように「ヒト」そのものが目標達成に直結する要素である業務も多くあります。そのため同じ組織に所属している「ヒト」がそれぞれ勝手に動いてしまうと、組織は正しい方向に進めません。円滑な組織運営を行うためにも「ヒト」は、最も力を入れるべき経営資源となります。
一方で「ヒト」は、感情や体調、環境といったものに影響されやすいものです。マネジメントを行う上で組織の管理者の力量が問われます。
組織運営の意味
現代は非正規社員、業務委託、時短勤務など、働き方が多様化しています。また、雇用のグローバル化も進んでいます。そのため、今後一つの組織の中には、生活環境やキャリア、文化も異なるメンバーが混在していくことが考えられます。
そこで求められるのが組織運営です。管理者はメンバー一人ひとりの適性や能力、価値観に合わせて仕事を割り振り、マネジメントを行う必要があります。管理者の采配がうまく機能し、各メンバーが能力を最大限に発揮できるようにすると、組織としての業務効率を高めることができます。
例えば、ある優秀な営業マンが営業活動以外にも書類作成や会議の準備、カスタマーサポートなどの業務を行っているとします。この営業活動以外の業務を、他のスタッフに分配して営業マンには営業活動のみを行ってもらうようにするとどうなるでしょう。営業マンは自分のスキルを十分に生かすことができ、業務が効率化するはずです。
「適材適所」の言葉通り、個々の適正を上手く仕事の役割に生かすことによって、互いの弱点を補い合う強い組織を運営することができます。強い組織をつくることはもちろん売上げ拡大にもつながりますし、競合他社が真似をしづらい自社の強みにもなります。そのためにも組織運営は欠かせないと言えます。
組織運営とリーダーシップの違い
「組織運営(マネジメント)」と「リーダーシップ」は似ているようですが実際には異なるものです。組織運営は組織全体の管理に関わることですが、リーダーシップはあくまでその一部のことを指します。両者の違いをそれぞれ説明します。
組織運営
組織運営とは、目標達成に必要な組織の要素を分析し、組織が機能するようにすること。戦略を立てたり、その戦略を実行するための仕組みを設けたりして計画を実行・管理します。また、営業マンをはじめとするメンバー一人ひとりの能力を最大限に発揮させることも求められます。成果はもちろん重要ですが、目標達成までの過程も重視して組織を管理していきます。
リーダーシップ
リーダーシップとは、組織の目標達成のためにスタッフを導いていくスキルのことです。経営者や各部署のリーダーには特にこのリーダーシップが求められます。メンバーを引っ張っていくという意味合いが強く、主にメンバーのモチベーションを維持管理していくことなどが求められます。
組織運営で大切な「組織の7S」
7Sとは、組織を考える上で必要な7つの経営資源の相互関係を表したものです。30年以上前に、アメリカのコンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーが提唱して以来、現在に至るまで組織の全体像を捉える際のフレームワークとして使われています。優れた企業では、この7つの要素がそれぞれ相互に作用しているとも言われており、企業の価値を示す一つの指針となっています。
また、この7つの要素は経営陣の意思決定によって変更可能な「ハードの3S」と、容易に変更できない「ソフトの4S」に分類されます。それぞれ一つひとつ、どんな要素があるか見ていきましょう。
戦略(Strategy)
戦略には、自社が競争優位に立っている理由は何か、その優位性を維持するためには何が必要か、また経営課題の解決の手段には何があるか、といった視点が求められます。これは市場や競合の変化を常に分析して、状況に応じて変える必要があります。
組織(Structure)
組織とは、集団が最大限のパフォーマンスを出せるように構成された形態のこと。上司と部下の関係や、どの事業で誰がリーダーシップをとっているか、といった点が目標達成に大きく影響します。
システム(System)
システムとは組織の活動を円滑にするための仕組みや制度のことです。具体的には目標管理制度、人事評価システム、会計システム、情報・業務管理システムなどが挙げられます。
スキル(Skill)
スキルとは文字通りスタッフ個人の能力のこと。また、自社が持つ独自の営業力や技術力も含まれます。他社と比較し、自社のどのスキルを向上させるべきかについて分析することも組織には求められます。
人材(Staff)
人材とは自社を構成する社員のことをいいます。「どんな人材がいるか」だけでなく「どんな人事を行っているか」「その人にあった働き方ができているか」を分析し、最適な人材の配置ができているのかをみる要素です。
スタイル(Style)
スタイルとは、その企業特有のビジネスの進め方のこと。会社の雰囲気、職場環境、組織の意思決定の流れ、また社風のことを指します。トップダウンやボトムアップなどのフローもこのスタイルの要素に含まれます。
共有価値(Shared Value)
共有価値とは、組織全体で共有するべき価値観や理念のこと。企業のミッションやビジョンは経営陣が理解していることはもちろんのこと、現場のスタッフにまで浸透しているか、また理解に齟齬がないかなどを分析します。
十分に落とし込まれていないと、掲げているミッションやビジョンと現場のメンバーの行動が異なってしまい、企業の印象も悪くなってしまう恐れがあります。
組織運営で身につけるべき能力
組織運営を始めても、管理する側に運営能力がなければ円滑に機能させることは難しいものです。ここでは、組織運営を行う上で管理者に求められる能力についてご紹介します。
目標を設定する力
まず、管理者には目標設定能力が求められます。現場の現状を把握し、どの程度が「頑張れば達成できる目標」となるのかを見極められる必要があります。目標設定が低すぎても高すぎても、メンバーのモチベーションは下がってしまいます。特に目標が高すぎる場合は、モチベーションが下がるばかりでなく、メンバーがついていけなくなってしまいます。「過剰なノルマが生産性をあげる」というのは間違いなのです。
「達成できるギリギリのライン」に目標をおくことで、ほどよい緊張感がうまれ、やる気や達成感を引き出すことができます。組織として達成すべき目標を理解・把握した上で、それを達成するための計画を立案し、最適な人員配置を行いましょう。
プロジェクトを管理する力
続いて、プロジェクトを管理する能力が求められます。これには目標達成までのプロセスを逆算し、計画を練れる計画力が含まれます。また、それぞれのプロセスに費やす時間・工数・労働力を把握した上でスケジュールを組む計画遂行力も含まれます。
立てた目標を遂行するためには、人を動かす仕組みづくりが欠かせません。全員が目標に向けて頑張れるような仕組みを作り、個人の努力が相乗効果を生み出すような環境を作ることが大切です。メンバーの進捗状況を逐一把握し、即座に問題解決やスケジュール調整を行い、目標達成まで導く能力を養いましょう。
モチベーションを管理する力
メンバーのモチベーションが下がると生産性が下がり、目標を達成することができなくなってしまいます。そのため、モチベーションを管理する能力も管理者には求められます。
メンバーのモチベーションを維持するために大切なのは、自ら率先して行動することです。指示・命令をするだけでなく、自分がやって見せることでメンバーの自発的な行動を促すことにつながります。
メンバーのモチベーションが低くなった時には、管理者の資質が問われます。このとき、精神論を元に指導をしてはいけません。営業成績が伸び悩んでいる営業マンに対して、実情を知らずに「もっとやる気を出せ」などと言うと、激励したつもりが、かえって営業マンのやる気を削いでしまうことになりかねないのです。もしかすると、その営業マンはやる気はあるものの、どう営業をしていいかわからないだけなのかも知れません。
そのため、モチベーションが低い時でも一定の成果を産むことができる仕組みづくりが管理者には求められます。管理者は、メンバーの適正・能力を把握した上で適材適所を考え、それぞれに応じた業務配分を行いましょう。また、それぞれのメンバーに適したサポートや指導も同様に行ってください。
コミュニケーション能力
組織運営を行う上で、人間関係は大きな役割を果たします。特に管理者には、上司と部下双方に対するコミュニケーション能力が欠かせません。
管理者は部下と信頼関係を築き、働きやすい職場環境を整える必要があります。経営陣との信頼関係構築も不可欠です。経営陣は売上げや利益を優先し、現場に指示・命令を出しますが、その際に管理者は現場の状況を経営陣に伝える必要があります。場合によっては指示そのものを変更してもらうこともあるでしょう。組織を円滑に動かすためには、現場と経営側双方の間を取り持つ高度なコミュニケーション能力が求められます。
継続的に組織運営を行なっていくためのポイント
組織運営を継続的に行うためには、先に挙げた能力を管理者が備えていることはもちろんのこと、メンバーの意見を定期的に取り入れていくことが大切です。そのため、普段からメンバーが何でも気軽に話ができる状態であることが重要です。また、意見を聞くだけでなく、その意見を何らかの形でできる限り反映させていくことにより、互いに信頼関係が生まれ、モチベーション維持にもつながります。
さらに、組織運営を行う上で、優秀な成果を挙げたメンバーにはインセンティブなどの報奨を与えて評価をしましょう。もしいくらがんばっても認められなければ、皆モチベーションが下がってしまいます。しっかりとした評価を行うことで、評価された本人だけでなく、周囲のメンバーにもライバル心が芽生えます。結果的に、全体の意欲が高まり、組織運営を継続していくことができるでしょう。
セールスハックスでは営業組織づくりのための手法をご紹介した記事もあります。「営業の組織力をアップするチームビルディングとは?」も参照ください。
まとめ
組織運営を実際に行おうとすると、多くの場合さまざまな困難な課題が立ちはだかります。特にコミュニケーション不足やモチベーションの低下など、人的な課題は少なくないのではないでしょうか。
しかし、人的な課題は人的な解決策を適用することができます。組織の成員であるメンバー一人ひとりの能力や価値観を管理者が把握し、それぞれの足りない部分を補い合う組織づくりを行うことを心掛けましょう。
各メンバーが、組織の掲げる目標を自分ごととして捉えて自主的に動くことができたなら、組織は自動的に動いていきます。より大きなパフォーマンスを生み出すことも可能になるでしょう。
「営業ワークフローと営業ツール標準化《実践ガイド》」では、営業を効率化しながら売上げを拡大することのできる手順を紹介しています。営業組織の強化を考えている経営者や営業マネージャーの方は、ぜひ参考にしてみてください。